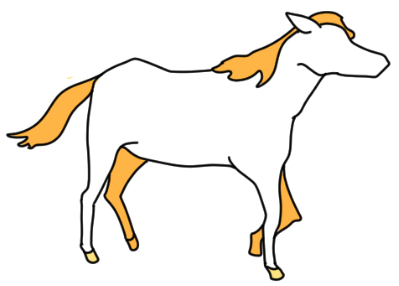2021年12月3日

この記事の作成者:
獣医学部動物応用科学科
南 正人
全国でシカが増え分布域を拡大し、農林業被害に加えて生態系への影響も大きくなってきました。植物がシカに食べられ、それに依存して生活していた昆虫などの小動物や野鳥などが影響を受けています。私たちの野生動物学研究室でも、シカの生態系への影響や牧場などの被害防除の研究、駆除したシカの資源としての利用などの研究を続けています。国内の多くの研究者がシカの数のコントロールや防除の研究をしています。
ところが、実はシカの行動については充分には研究されていません。私はシカの行動についての研究を続けています。調査地は宮城県の牡鹿半島の先にある金華山という離島で、黄金山神社という神社周辺にいる人に馴れたシカ約150頭に名前をつけて行動観察を33年間続けています。


シカのオスは秋の発情期にメスをめぐって闘うのですが、その作戦が多様であることがわかりました。
神社周辺は疎林で、メスはある程度集団でやってきて日中は神社境内に滞在しますので、オスはその集団がやってくる場所を守ってなわばりを作っていました。見通しがよいので、侵入してくるオスを排除しやすいようです。
ところが、森林ではメスがバラバラで行動することが多くてメスを囲うことができません。また、見通しが悪いので、侵入してくるオスも出て行こうとするメスも見逃すことが多く、なわばりを作らないのです。
さらに、神社の北に広がる草原では、メスは集団になるのですが、大きく移動するので土地を守るなわばりではなく、このメス集団を守って一緒に移動していました。
ひとつの島の中でも、異なる環境では異なる社会をもっていたのです。
さらに、神社周辺では、こんなことも観察されました。1992年モヤシというオスの栄養状態が良く、秋に強大な体格になりました。神社境内では、どのオスもモヤシに勝てないのです。そうなると、モヤシは前年にはつくっていたなわばりをつくる必要がなくなりました。どこに行っても強いので、発情したメスを見つければいつでも交尾できるのです。モヤシは神社境内全域を徘徊してメスを探すようになりました。
しかし、次の年はライバル達との体格や体力に差が無くなり、モヤシはなわばりをつくったのです。つまり、どのような社会になるかは、環境だけでなく、オス同士の闘争力の差にも影響されていたのです。

発情期にはメスを巡って時には死につながる大けがをするほど激しく闘うオス達ですが、発情が終わるとオス同士で闘うことはほとんどありません。時には、集まって座っていたりします。メスは血縁関係にあるメス同士で集まるのですが、このオスの集団は血縁とは関係なさそうです。この時期のオス同士の関係はまだよくわかっていません。また、攻撃性と親和性がどのように切り替わるのかも野外での観察だけではよくわからないのです。
最近、これらのシカの糞からホルモンを抽出して調べる準備を始めました。ストレスを感じると分泌されるというコルチゾールの測定のためです。シカ同士の関係で生じるストレスを測定したり、人に馴れている個体と馴れていない個体で人に出会った時のストレスを評価できる可能性があります。この研究は野生動物の一部が畜産動物になった家畜化の過程を調べることにつながるかもしれません。

2024年3月21日
タヌキトンネルが教えてくれた!野生動物を継続観察する大切さ

2024年1月26日
忠犬ハチ公はなぜ有名に?動物行動学者がハチを通してヒトと動物の関係を見直してみる

2022年3月2日
私たちの体に必要な油

2022年1月17日
野生鳥獣肉の風味

2021年11月15日
小鳥の家禽種と野生種の違いにオキシトシンが関与?

2021年10月26日
ニホンオオカミがイヌの起源!?